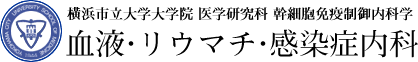2023.11.14
同門会誌 令和5年度:研究室だより
研究に関する近況
血液・免疫・感染症内科学
國本 博義
2018年度に入局して以来、血液グループ内に基礎・橋渡し研究グループ及び研究体制を新たに構築するため尽力してきた。これまで4名の博士課程大学院生(血液グループ3名、本学小児科大学院生1名)と1名の修士課程大学院生の研究指導を行うとともに、私自身も診療・教育の傍ら独自のプロジェクトを進めている。
我々の研究グループでは、急性骨髄性白血病(AML)・骨髄異形成症候群(MDS)をはじめとする骨髄系腫瘍の分子病態に主眼を置き、マウス・ヒト白血病細胞株、白血病動物モデル、患者骨髄検体を駆使した研究を展開している。近年の次世代シーケンス技術の進歩により、AMLを筆頭に骨髄系腫瘍にみられる遺伝子変異及び染色体コピー数異常の全貌はほぼ明らかにされた一方、個々の患者にみられる遺伝子変異・コピー数異常のプロファイルは非常に多様であることも判明した。このことは個々の患者の腫瘍発生に至る過程や腫瘍の特性を規定する分子基盤が多彩であることを示しており、症例ごとの臨床像や抗がん剤に対する感受性の違いにも相関していると考えられる。我々は、高リスク骨髄系腫瘍で高頻度に遺伝子変異がみられるエピゲノム因子・シグナル因子、そして3番及び7番染色体の異常に着目し、これらの遺伝子変異、染色体異常がどのように協調して腫瘍発生に至るのか、その分子メカニズムを明らかにすることを目指し研究を進めている。また近年健常高齢者に多く前白血病状態と考えられるクローン性造血における造血幹細胞のクローン拡大進展機構の解明を目指した研究も進めている。我々は、3番と7番の染色体異常を有し、MDSからAMLへ進展した高リスクAML患者由来の新規白血病細胞株YCU-AML1を樹立し (Kunimoto et al. HemaSphere 2020)、現在このYCU-AML1を駆使して高リスクMDS/AMLに対する新薬開発を目指し、製薬企業から候補となる化合物の提供を受けて共同研究を進め、有望な知見を得つつある。さらに小児科との共同研究として、高リスク小児急性骨髄性白血病の抗がん剤耐性機構に関する研究も進め、新しい知見を得つつある。YCU-AML1プロジェクトと小児科との共同研究プロジェクトは2023年に国内外の学会で成果を発表したのち、論文化を目指している。また福浦とセンター病院のMDS患者の臨床情報とクリニカルシーケンスデータを統合した新しいMDSデータベースを構築し、今後の臨床研究に活用したいと考えている。特にリウマチグループとの共同研究としてVEXAS症候群に合併するMDS症例の臨床像、遺伝子変異プロファイルは日本血液学会英文誌にも報告しており(Kunimoto et al. Int J Hematol 2023)、今後症例数を増やして解析を進めていく。
最後に、これまで多くの研究を遂行し大学院生を育成するにあたり、福浦の血液グループの諸先生方、YACHT並びに同門会の諸先生方より多大なご協力を戴いたことに深く感謝申し上げたい。また公的研究費や多くの民間財団から研究費の支援を戴いたこと、何よりも研究のために多くの患者様から貴重な骨髄検体のご提供を戴いたことを付記しておく。
一覧に戻る
2023.11.14
同門会誌 令和5年度:研究室だより
膠原病疾患病態の分子メカニズムの解析と疫学研究
吉見 竜介
私たちは,膠原病疾患の病態形成に重要と考えられる遺伝子の発現制御機構や機能を分子レベルで解析し,新しい治療戦略の確立や創薬に役立てることを目標にしています.膠原病疾患は一般的に自己免疫反応によって引き起こされる炎症が原因であると考えられていますが,その発症機序はよくわかっていません.近年,Toll様レセプターなどのパターン認識受容体を介したシグナルの異常が自己免疫反応につながることが知られるようになりました.私たちはこれらのシグナルと関連が深いE3ユビキチンリガーゼファミリーであるTRIMファミリーとその基質となる転写因子群IRFファミリーに注目しています.
TRIM21は,IRFファミリーをユビキチン化することによって炎症性サイトカインやI型インターフェロンの産生を制御しています.また,TRIM21によってユビキチン化されるIRF8は樹状細胞やマクロファージにおいてインテグリンの発現亢進を介するTGFβシグナル伝達系を活性化するなど,自己免疫反応に重要なTh17細胞の働きを強めます.また,TRIM21は全身性エリテマトーデスやシェーグレン症候群の患者血清中にみられる抗SS-A抗体に対応する自己抗原でもあります.私たちはまずTrim21欠失マウスの表現型解析によって,TRIM21がE3ユビキチンリガーゼ活性によってIRF3やIRF8の発現を生体内で調節していることや,いくつかの炎症性サイトカインの産生に抑制的に働くことを明らかにしました.神山玲光先生は,TRIM21が生理的にI型インターフェロン(IFN)の産生を抑制しており,全身性エリテマトーデス(SLE)患者において血清中の抗TRIM21抗体が細胞内のTRIM21のI型IFNの産生抑制作用を阻害する可能性を示しました(Kamiyama R, Mod Rheumatol. 2018).また國下洋輔先生は,Trim21欠失MRL/lprループスモデルマウスを用いてTRIM21がB細胞の形質芽細胞への分化能や抗体産生能を抑制することを発見し(Kunishita Y, et al. Front Immunol. 2020),さらにSLE患者の血清抗TRIM21抗体陽性群では陰性群と比較してB細胞の形質芽細胞への分化能や抗体産生能が亢進していることも明らかにしました(Kunishita Y, et al. Lupus. 2021).
これらの知見からは,SLEにおいてTRIM21の発現亢進は病勢を抑制しようとする生体防御反応であり,血清抗TRIM21抗体がこれを阻害しているのではないかという仮説が考えられます.これを証明するためには,細胞質内の自己抗原に血清中の自己抗体がどのように関与するのかを明らかにすることが課題であり,櫻井菜月先生が現在この点を解明するために研究しています.抗SS-A抗体は全身性強皮症患者の血清中にもみられ,間質性肺炎との関連が示唆されています.全身性強皮症におけるTRIM21の病的役割を調べるために,吉岡裕二先生はTrim21欠失マウスを用いて全身性強皮症モデルや肺線維症モデルの作成を手掛けています.様々なTRIMファミリータンパクと炎症に関わるタンパク質複合体であるインフラマソームの関連が報告されていることから,國下先生はTRIM21のインフラマソームにおける役割を調べるなど,TRIM21研究をさらに展開しています.また,最近TRIMファミリータンパクが細胞内の主要な分解系であるオートファジー・リソソーム系において標的を認識する受容体や受容体制御因子の役割を担っていることが明らかになってきています.鈴木直樹先生は,TRIM21を中心としてTRIMファミリーによるオートファジー制御作用の膠原病病態での役割を解析しています.
パイリン(TRIM20)は家族性地中海熱(FMF)の責任遺伝子MEFVによってコードされ,好中球や単球・マクロファージに発現してインフラマソームを構成し,カスパーゼ-1の活性化やインターロイキン-1βの成熟を制御します.一方で,パイリンの変異がFMFとして過剰な炎症を誘発するメカニズムは不明でした.寒川整先生は好中球におけるパイリンの結合タンパクとしてβ2ミクログロブリンを同定し,パイリンのM694V変異がパイリン-β2ミクログロブリン結合に対するカスパーゼ-1サブユニットp20による阻害を弱めることを発見しました(Samukawa S, et al. Sci Rep. 2021).
TRIM39はTRIMファミリーの中でもTRIM21と同じサブグループに属し,非常に構造がよく似ているTRIMタンパクです.TRIM39遺伝子はベーチェット病や皮膚エリテマトーデスの疾患感受性遺伝子として同定されておりますが,TRIM39分子の免疫学的な機能についてはこれまでに報告がほとんどありません.現在,小宮孝章先生がTrim39欠失マウスの表現型解析を行っています.すでに,免疫グロブリンの産生や腸管免疫においていくつかの興味深い異常を見出しており,TRIM39と病態との関わりが注目されます.
近年膠原病疾患においてエピゲノム修飾の変化による遺伝子発現の異常が報告されていますが,IRF8遺伝子もN-アセチルグルコサミン転移酵素OGTによってエピゲノム修飾による発現調節をうけることが分かっています.OGTはヒストンにO-結合型N-アセチルグルコサミン(O-GlcNAc)を付加して様々な遺伝子の発現をエピゲノム的に促進する酵素です.O-GlcNAc修飾は,2型糖尿病モデルマウスのマクロファージにおいて炎症性サイトカインの発現を調節するNF-κBの活性化に関与することが明らかにされており,自己免疫現象を含む広範な免疫応答への関与も示唆されます.そこで,秀川智春先生はOgt欠失マウスの免疫学的な異常を解析するとともに,Ogt欠失膠原病疾患モデルマウスを作成して膠原病病態との関連を調べています.
私達は膠原病に関する様々な疫学研究にも取り組んでいます.当科は全国規模のSLEレジストリ研究に参画しており,その中心的な役割を担っております.このレジストリデータを用いて秀川智春先生は,SLEに用いられる抗マラリア薬であるヒドロキシクロロキンが,疾患活動性のコントロールのみならず重症感染症の合併を抑制する作用を持つことを明らかにしました(Hidekawa et al. Front Immunol. 2023).その他にも,SLEにおける高齢発症例の特徴(櫻井菜月先生; 投稿中)や肥満と疾患活動性の関連(鈴木直樹先生)など,様々なリサーチクエスチョンを立てて研究を行っています.
杉山裕美子先生は皮膚筋炎・多発性筋炎の疫学研究として予後不良因子や感染症リスク因子を明らかにした研究(Sugiyama et al. Arthritis Res Ther. 2018)を発展させ,予後や治療反応性を推測できるバイオマーカーとなるマイクロRNAを探索しました.近年,タンパク質をコードしない非翻訳領域から成る22塩基前後のRNA分子マイクロRNAが遺伝子の転写後調節に関与することが明らかとなり,がんや免疫の領域において病態への関与や疾患マーカーとしての有用性が注目されています.このうちmiR-1というマイクロRNAは筋細胞の分化増殖に関与し,炎症性筋疾患の筋組織においてその発現が低下することが報告されています.杉山先生は皮膚筋炎・多発性筋炎において血清中のmiR-1量はむしろ増加しており,間質性肺炎合併例においてmiR-1の量が多いほど治療開始後のステロイドが減量しにくく重篤な感染症の合併が多いことを明らかにしました(Sugiyama Y, e al. Mod Rheumatol. 2020).杉山先生は現在,抗MDA5抗体のエピトープの解析をカロリンスカ大学との共同研究として手掛けております.
以上,私たちのグループにおける基礎研究および疫学研究を紹介いたしました.基礎研究はどれも数年先すぐに臨床の現場に反映されるという性質のものではありませんが,十年先に出現する画期的な新規治療法の土台となる可能性を秘めています.コツコツと新しい知見を生み出していく地道な姿勢を大事にしながら,これからも研究活動を続けてまいりたいと思っております.
一覧に戻る
2023.11.14
同門会誌 令和5年度:留学だより
National Human Genome Research Institute
國下 洋輔
2013年に入局したリウマチグループの國下洋輔と申します。
私は、2023年8月より、米国のNIH(National Institutes of Health)のNHGRI(National Human Genome Research Institute)にあるDaniel Kastner先生の研究室にVisiting Fellowとして留学しております。まだ、渡米してから1ヶ月程度しか経過しておらず、やっと生活環境の準備が整ってきたというところで、研究についてお伝えできることがほぼなく、今回は、主に留学先の研究室の紹介をさせていただこうと思います。
ご存知の先生も多いかと思いますが、Kastner先生は石ヶ坪前教授(現:名誉教授)がNIHへ留学された際の研究室仲間であり、その後、NIHで研究室を持たれ、この研究室には、今まで、当科の桐野先生、本学眼科学の竹内先生、本学呼吸器内科学の堀田先生が留学されてきました。Kastner先生はWikipediaでも紹介されているような大変ご高名な先生で、自己炎症疾患の提唱者であり、炎症性疾患の遺伝学的研究の世界的第一人者です。それにも関わらず、いつもフランクに話しかけてくださり、当初、まだNIHの入館証がなく、職員エリアに入れない私を毎日自ら迎えに来てくださるような大変優しい先生です。これまで関わってきた先生方のこともよく覚えておられ、Yoshi、Yohei、Masa、Nobuとファーストネームで呼び、今も気にかけておられ、そういったところからも優しいお人柄が垣間見えます。そういった会話の中では、私も上記先生方をファーストネームで呼ばせていただくわけですが、帰国した際には、日本モードへ切り替えるよう気をつけたいと思っております。
研究に関しては、もっぱら遺伝学的な研究と想像していましたが、Kastner先生はNIHの内外に数多くの門下生を輩出され、現在も数多くの共同研究をされており、そういった先生方と協力し、遺伝学的な解析に加え、その機能解析といったWetな実験も自ら行い、研究を進めていくことになりそうで、楽しみにしております。研究の中で、何かしら教室に還元できる財産を得て、帰国できればと思っております。
最後になりますが、今回の留学に際して、研究のご指導に加えてKastner先生との縁を繋いでいただいた桐野洋平先生、研究のご指導やNIHの情報をご教示いただいた吉見竜介先生、仲野寛人先生、留学助成応募に際して数々の御助力をいただいた長岡章平先生、ご支援をいただいた中島秀明教授ならびに同門会の諸先生方に心より御礼申し上げます。今後とも、ご指導・ご鞭撻のほど、何卒、よろしくお願い申し上げます。
一覧に戻る
2023.11.14
同門会誌 令和5年度:専攻医紹介
専攻医紹介
附属病院 血液・リウマチ・感染症内科
本多 主税(令和2年卒)
日頃より大変お世話になっております。専攻医2年目の本多と申します。
昨年度は横浜南共済病院、今年度は横浜市立大学附属病院で研修させていただいております。昨年度は外来で関節リウマチを主に診療しておりましたが、今年度は病棟業務が中心となり、全身性疾患が多く重症度も高いため貴重な経験をさせていただいております。
病棟では同じく専攻医の市川先生、北堀先生、また指導医として仲野先生、副島先生、濱田先生と働き、副島先生に直接指導いただきとても有意義な日々を送ることができてきています。また。桐野先生、吉見先生、峯岸先生にも病棟業務に関してアドバイスをいただいており安心して仕事ができています。
私が研修医として大学病院のリウマチ科で研修していたときとは体制が変わり、難しい場面もありますが副島先生や他先生方のアドバイスや後押しもあり主体的に診療をさせていただいており充実した日々を送っています。
今まで全く経験のなかった疾患、特にVEXAS症候群の患者様の診療やその難しさを日々感じていますが膠原病診療は原因不明の経過から診断、治療を行うことがほとんどであり患者様の感謝のお言葉をいただくことも多く一生涯にわたって自身の専門領域にしたいと考えております。
まだまだ勉強が足りない部分も多く、一生涯をかけて学んでいかなくてはなりませんが大学病院で診療を経験させていただき、膠原病診療の奥深さ、難しさ、またやりがいを改めて感じています。
医局の雰囲気も良く、恵まれた日々を送ることができていることをこの場を借りて感謝申し上げます。
以上、簡単ではございますが寄稿文とさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。
一覧に戻る
2023.11.14
同門会誌 令和5年度:専攻医紹介
専攻医紹介
センター病院 リウマチ膠原病センター
張田 佳代(令和2年卒)
専攻医2年目の張田佳代と申します.現在,横浜市立大学附属市民総合医療センターのリウマチ膠原病センターに勤務しており,大野滋先生や岸本大河先生のもとで研鑽を積ませていただいております.医業に従事し4年とまだまだ短いですが,大学病院への勤務は初めてであり,これまでに経験したことのない複雑な病態や多数の診療科にまたがって診療計画を組まなければならない患者さんの診療にあたることが増え,実臨床の厳しさと楽しさを痛感する毎日です.特に,生命予後には影響は大きくないものの日常生活に大きな支障をきたす病態(多発単神経障害や関節リウマチによる骨破壊や強直による疼痛,変形性関節症の炎症性疼痛に対する治療法など)の対処に難渋することが多く,患者教育やリハビリの指導含め満足度高く管理することを目下の目標としております.諸先輩方がどのようにマネジメントされているか大変興味がありますので,もしお会いすることがありましたらお聞かせいただけますと非常に嬉しく思います.
私生活では横浜市を離れて東京都に移り住むこととなり,はじめて住民票が横浜市以外になりました.今までの2倍近く通勤時間がかかることに辟易しておりますが,これまで通り横浜の医療に貢献できるように邁進していくので,今後とも何卒よろしくお願い申し上げます(なお,苗字はまだ変わる気配はありませんのでご安心くださいませ).
一覧に戻る
2023.11.14
同門会誌 令和5年度:専攻医紹介
専攻医紹介
附属病院 血液・リウマチ・感染症内科
北堀 弘大(令和2年卒)
横浜市立大学血液・免疫・感染症内科学 膠原病グループの専攻医2年目の北堀弘大と申します。
昨年度1年間は国立横浜医療センターで研修させて頂きました。内科診療の基本も分からないような専攻医1年目でしたが、井畑先生・関口先生の温かいご指導を賜り、リウマチ・膠原病学のみならず内科一般の基本を勉強させて頂きました。
本年度は、横浜市立大学附属病院で勤務しております。大学病院という性質から、より膠原病に特化した患者さんを扱っており、重症な症例を診療する場面が昨年度より多いことを実感しております。教科書的には稀とされているような症状で、患者が急変する場面を目の当たりにすることもあり、自分の診療能力の未熟さを歯がゆく感じることも多くあります。一方で、これらの経験を通じて患者さんの訴えや身体所見等について以前よりも敏感になり、有意所見か疑ってかかる姿勢が少しずつ養われていると感じています。
疾患概念ができてからまだ日が浅い疾患に対しても、豊富な知識や経験値をもとに的確に治療の方向性を決めている先輩の先生方と自分とでは、まだまだ高い壁があることを感じております。先輩の先生方のように患者さんに具体性のある情報を提供し、より良い治療方針を決定できるように今後とも精進して参ります。
一覧に戻る
2023.11.14
同門会誌 令和5年度:専攻医紹介
専攻医紹介
センター病院 リウマチ膠原病センター
水野 広輝(平成31年卒)
リウマチグループ専攻医3年目の水野です。専攻医として働き、早くも2年半が過ぎました。研修医の先生との学年差もわずかですがひらきつつあり、会話のなかでジェネレーションギャップを感じることが出始めています。
今年度はセンター病院で勤務し、外来2コマと時々の新患外来を担当しています。昨年度の横浜医療センターよりもSLEをはじめとした膠原病の患者さんが多いことを身をもって感じています。ガイドラインも参考にはしますが、論文検索を要する機会も増えてきたように感じます。今年度も分からないときは上級医に気軽に(自分で言ってよいのか!?)相談できる環境にあり、感謝しています。入院時は重症であった患者が、数か月後に元気で外来通院してもらえるとやりがいを感じ、リウマチ科で良かったなと感じます。
私生活においては、2022年のクリスマスイブに長男が誕生しました。毎朝、教育テレビを一緒に観ています。まだ発語はないですが、初めての言葉はパパであることを願っています。
短期的には内科専門医にむけてそろそろ締め切りのJ-OSLERというレポートを頑張っていきます。長期的には、自己研鑽に励み、医師として成長していきたいと思っております。まだまだ未熟ではありますが、今後ともよろしくお願いいたします。
一覧に戻る
2023.11.14
同門会誌 令和5年度:専攻医紹介
専攻医紹介
センター病院 血液内科
髙山 康輔(平成31年卒)
同門会の先生方、いつも大変お世話になっております。入局3年目・血液Gの髙山 康輔と申します。昨年度は済生会横浜市南部病院で、今年度は市民総合医療センターで勤務させていただいております。
南部病院では藤田先生・石井先生のご指導の下、高齢者の一般内科診療から自家移植を含めた血液診療まで幅広く経験をさせていただきました。非常に有意義かつ楽しい南部病院での勤務も終盤に差し掛かった頃、当直などの疲労も祟ってか肛門周囲膿瘍→痔瘻を発症し、関係の方々には現在に至るまでご迷惑をおかけしております・・・。
肛門周囲膿瘍発症時より松島病院でお世話になっておりますが、本当にいい病院なので松島病院について勝手ながら紹介したいと思います。自分が最初に緊急入院した際にはお化けが出そうな院内でしたが、2023年5月に新築移転をしました。痔瘻に対する根治術は1-2週間程度の入院が必要になるため、タイミング的にも新築移転してからのほうがいいよ、と担当医に勧められたため今年の7月に入院して手術を受けました。場所はほとんど変わらず戸部駅の近くなのですが、完全に少しお高めのホテルのような造りとなっています(入院病棟に入るにはカードキーが必要です)。快適性の反面、入院病床のほとんどが差額ベッドとなっており、無料の4人床もあるにはあるのですが、Wi-Fiが使えない(!)などの制限があるため、万が一入院される際は有料部屋の利用をお勧めします(個室はかなり高額なため自分は2人部屋にしましたが、それでも1日1万円以上の差額がかかりました)。退院後の現在も通院を続けていますが、胃腸科と肛門科だけで外来ブースが20以上あるなど、真に胃腸+肛門に特化した病院であることを感じます。受診される際の注意点として、午前中は非常に込み合っており、時に怒号が飛び交っているため午後の受診をおすすめします。
取り留めのない文章、失礼しました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
一覧に戻る
2023.11.14
同門会誌 令和5年度:専攻医紹介
専攻医紹介
神奈川県立がんセンター血液内科
香月 健吾(平成31年卒)
入局3年目の香月です。同門会の皆様におかれましては、日頃手厚い指導をいただきありがとうございます。
4月より神奈川県立がんセンター血液内科に異動となりました。初めての施設、初めてのカルテ、初めての病棟スタッフと慣れないことずくめで、最初は点滴のオーダー1つ立てるのも苦労しておりました。様々な違いにもようやく順応でき、他のことにも手が回るようになってきた今日この頃です。
疾患も前年まで在籍していたセンター病院とは毛色が全く異なり、移植を中心に白血病治療のイロハを学んでおります。治療戦略の立て方、合併症への対応、さらには人工呼吸や透析といった集中治療の分野まで、田中先生・立花先生から幅広く指導をいただいており、お二人のサポートがなければ到底半年は過ごせなかったと思います。この場をお借りして御礼申し上げます。
また昨年度後半より、藤澤先生・宮崎先生ご指導の下、臨床研究にも取り組みを始めました。データ収集や統計解析の手法など、こちらも勉強になることばかりです。先日の血液学会にてその一部を発表させていただき、今後さらに研究を進め、何か形を残せればと思っております。また立花先生ご指導の下、Case reportの執筆も行っており、臨床以外にもやるべきことが山積みとなっております。体を壊さない程度に日々頑張ってまいります。
風が冷たく感じる日も増えてまいりました。同門会の皆様におかれましてもご自愛ください。
一覧に戻る
2023.11.14
同門会誌 令和5年度:専攻医紹介
専攻医紹介
附属病院 血液・リウマチ・感染症内科
市川 健斗(平成31年卒)
横浜市立大学附属病院血液リウマチ感染症内科リウマチグループの市川と申します。入局後1年目は南共済病院、2年目はセンター病院でお世話になりました。
昨年度は臨床研究においても多くの先生のご協力を頂きました。この場を借りて御礼申し上げます。
今年度から大学病院勤務となりました。
病棟チームは新体制であることに加え、平均入院患者数が例年の倍以上で推移していたこともあり、あわただしい日々が続いておりました。
半年経過し、ようやく当院のシステムに慣れ、病棟も落ち着いてきたように思います。臨床と学術活動、J-OSLER、プライベートの両立は大変ではありますが、リウマチ学に対する知的好奇心が支えになっています。
大学病院ということもあり、複雑な病態をきたしている症例が多いため、日々知識のなさを痛感する期間が多くあり、気を引き締めているところです。
中には望まない転機をたどる症例を経験し、悔しい思いをすることもありました。
その経験からその症例の病態を深く掘り下げ、来年度から大学院に進学し、病態解明の研究を行いたいと考えております。
近況としましては、借家ではありますが、一軒家に転居しました。
長年アパートやマンションに住んでいましたが、隣人に恵まれず毎回騒音トラブルに巻き込まれていましたので、ようやく騒音のない安眠を手に入れることができてほっとしております。
最近は家具を買い替えたり、観葉植物を買ってみたり、生活の便利グッズをそろえたりすることが日々の息抜きになっています。
以上、簡単ではございますが、近況報告させていただきました。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。
一覧に戻る