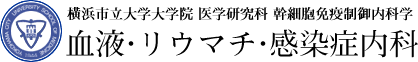2023.11.14
同門会誌 令和5年度:センター病院の現況
センター病院 感染制御部
比嘉 令子
8月に今年度の国公立大学附属病院感染対策協議会の教育作業部会ブロック別研修会に感染制御部メンバーとして参加してきました。
今回は群馬大学の主催でしたので、前橋駅から車で15分ほどの距離の群大の附属病院内での会合となっており、日帰りの参加でした。
朝9時開始という比較的早い時間でしたが、横浜からは早朝出発でかろうじて間に合うため(前泊の宿泊費が出ないパターンの出張ですね)タイトなスケジュールを気にしつつ、新幹線やタクシー含めて乗り継ぎ、無事に若干の余裕をもって現地入りすることができました。
群馬大の先生方が明るくユーモアがあったということもあり、特に有意義かつ楽しい研修会でした。職種別に分かれて会議では各議題についてそれぞれの施設の状況を聞けて大変参考になりました。
例えば、COVID-19の隔離解除基準一つをとっても施設ごとに異なっている現状だというのがよくわかります。
センターでは隔離基準については日数+臨床症状改善状況で見る日数ベースの基準と抗原定量陰性化を確認する検査ベースの基準、二通りのやり方を明示していますが、そもそもコンディションの悪く臨床症状の改善がはっきりしない状態で、かつ抗原定量がなかなかカットオフ値を下回らない場合などについては、苦労します。
罹患からずいぶん日数が経過している。抗原定量の値としても陽性基準を満たすものの感染初期から比べれば定量値としては相当に低い。こんな場合にはまあ、隔離解除しても実害はないと思うんだけど……とは思いつつ、涙を呑んで抗原定量陰性化をもって隔離解除をお願いしております。
センターの感染制御の立場からはそのような風にせざるをえないなか、SARS-CoV-2のウイルス培養を行いそれで判断しているという施設もあり、かかるコストやそれが当院で現実的かどうかははさておき、判断がわかりやすくてうらやましい! とは思いました。
院内については隔離解除に未だに慎重な一方な態度をとらざるを得ない一方で、世相は感染対策を緩める傾向が顕著であり、医療従事者も家庭や交友関係を中心に罹患しやすいというちぐはぐさには大変困っております。
リスクのある層とない層の分断につながっているという印象です。
ワクチンも劇的な効果は見込めず、副作用は軽いがばかにならない。
決め手となる一手を欠いたまま事態としては膠着していると感じられ、特に批判というのでは全くないのですが後世この時期は歴史家によってどのように書かれるのかしら、とそこには興味を持っております。
一覧に戻る
2023.11.14
同門会誌 令和5年度:センター病院の現況
センター病院 リウマチ膠原病センター
大野 滋
2023年度のリウマチ膠原病センターは岸本先生に加え、専攻医の水野先生・張田先生が勤務してくれています。
非常勤の上田先生・加藤先生にも引き続き外来のお手伝いをしていただいています。
ポストコロナの新たな診療体系を構築する必要があり、紹介患者の確保、逆紹介の推進、入院患者増を求められています。
おかげさまで病院が設定した目標値をほぼクリアできそうな状況です。
いつも患者様をご紹介いただきましてありがとうございます。
引き続きよろしくご協力のほどお願いいたします。
一覧に戻る
2023.11.14
同門会誌 令和5年度:センター病院の現況
センター病院・血液内科近況報告
藤澤 信
本年度のセンター病院血液内科は部長の藤澤信(診療教授)のほか、宮崎拓也(診療講師)、中嶋ゆき(助教)、石井好美(助教)、日比野勇人(指導診療医)、髙山康輔(専攻医3年目)、山ノ川晴花(専攻医1年目)および横浜市民病院専攻医2年目の新村昂平からなる計8名のスタッフで診療しております。
また、昨年度に引き続き、渡辺玲奈および松村彩子には非常勤として、それぞれ週に1回の新患外来を担当して戴いており、非常に助かっております。
紙面を通じまして感謝申し上げます。
今年度はコロナ禍から明けたとは言いつつも、通院中の患者が発熱した場合には高い頻度でcovidが陽性になっており、重症化するケースは少ないものの、免疫不全状態の患者が多い当科にとってはまだまだ緊張を要する日々が続いております。
とはいえ病院自体では診療抑制などの制限も無く通常診療での運用となっております。
昨年度の当科の入院実績として、一日平均入院患者数は29人、病床稼働率は121.0%と定数(24人)を大きくオーバーしております。
また、外来患者数は13,149人(一日平均54人)と例年とほぼ同数でありましたが、新患患者数は584人と減少(一昨年比マイナス58人)し、新規患者数の増加を病院管理部から求められており、今年度の課題の一つと挙げられております。
移植医療について、当院では2000年の開院から2022年度末までの23年間累計で、390件の同種移植(血縁者間骨髄:64件、血縁者間末梢血:67件、非血縁者間骨髄:161件、非血縁者間末梢血:4件、臍帯血:94件)、174件の自家移植、合計で564件の造血幹細胞移植が行われました。近年では年間15-20件の同種移植と10件前後の自家移植を行っており、同種移植は2023年中に累計400件に到達すると想定されます。
昨年の当科の業績として、筆頭・共著合わせて4編の英語論文がpublishされ、3編の日本語論文、および海外3演題を含む20演題が各学会で発表されました。
昨年の論文業績が例年に比較して少ないことは反省点でありますが、今年は症例報告や臨床研究を多く手掛けておりますので、来年度以降には良い報告ができるよう努力したいと思います。
今後も諸先生方のご指導・ご鞭撻を賜りながら、血液内科の更なる発展のために研鑽に励む所存であります。
宜しくお願い申し上げます。
(文中敬称略)
スタッフ一同 (病院会議室にて)

前列左から、新村・山ノ川 後列左から、髙山・日比野・藤澤・石井・宮崎・中嶋
一覧に戻る
2023.11.14
同門会誌 令和5年度:大学の現況
附属病院・感染症グループ 近況報告
横浜市立大学医学部 血液・免疫・感染症内科学
助教 寒川 整
附属病院では感染制御部長を兼任する加藤講師、寒川そしてリウマチGから副島助教、仲野助教にお手伝い頂きながら感染症コンサルテーション業務およびHIV診療を行っています。
当院は神奈川県エイズ治療中核拠点病院に選定されおり、感染症分野でも特に高度なHIV診療を担っています。近年日本では新規HIV診断者数が減少傾向となっていますが、当院へ紹介されてくる未治療HIV感染者数は一行に減る気配はなく、例年通りとなっています。中でも最近の傾向として50歳以上のAIDS発症例が多く、また異性間の性的接触による感染も増えてきているような印象があります。今後HIV感染者を見逃さないためには、HIV感染=若年男性間の性的接触による感染といった固定観念を見直す必要がありそうです。
神奈川県には当院に加えて、今年新たに横浜市民病院が中核拠点病院に選定されました。さらに15の治療拠点病院が存在していますが、近年では担当医師不在のためHIV診療を縮小してく施設も少なくないようです。一方でHIV感染が長期予後を期待できるようになった反面、患者の高齢化が進んでおり、HIV診療ができる病院が各地域に存在することが望まれています。幸いなことに、HIV陽性者を受け入れてくださるリハビリテーション病院や介護施設は年々増えてきており、転院先が見つからずに困る機会は少なくなってきました。しかし急性期病院においては未だにHIV陽性者の診療はHIV感染と関連がない疾患でも拒否されてしまうことが多々あります。看護師や介護士などコメディカルはHIV感染者の診療に抵抗がない中、肝心の医師がHIV感染者の診療に難色を示しているといった背景が要因として考えられます。今年の2月には藤沢市医師会でHIVの講演をさせて頂く機会があり、プライマリーケアに携わる先生方からもHIV早期診断や高齢HIV患者への往診対応について前向きなお言葉を頂くことができました。これからのHIV感染症は幅広い地域と施設で診療していく疾患へ変化していくことが必要であり、その流れを作るために、診療だけでなく研修会等にも力を入れています。
神奈川県HIV診療のパラダイムシフトを起こすべく、同門会の先生方には日頃からご支援頂いている中で大変恐縮ではありますが、今後ともご協力およびご指導の程、よろしくお願い申し上げます。
一覧に戻る
2023.11.14
同門会誌 令和5年度:巻頭言
会長挨拶
with coronaの時代下で
2023年 9月25日
血液・免疫・感染症内科同門会
会長 児玉 文雄
同門会の皆様、如何お過ごしでしょうか。これまで3年有余、社会活動制限の元凶となって来た新型コロナウイルス感染症が感染の波を繰り返しながらも入院患者数、重症化などが漸減し今年5月8日からインフルエンザと同様に第5類感染症扱いとなり、全数把握から定点把握となりました。終息した訳ではありませんがそのような状況となり先ずはほっとしました。そんな中、今年7月6日に2019年7月16日以来、実に4年振りに実会合同門会・納涼会を行うことが出来、私達の同門会史上、記念的会となりました。4年を経てもお互い殆ど変わらず元気に談笑、懇親を深め楽しい会になりました。
現在進行中の第9波の週間発生数(厚労省)を見ると9月初旬をピークに横這い状況(この文記載の今は9月24日)が続いています。新型コロナウイルスは常に変異しているので特定の変異株に対して開発されたワクチンが汎用可能となる頃には更に変異を重ねた変異株が主流となっているのがこれまでの状況です。9月20日からオミクロン株派生型XBB.1.5に対するワクチンが供給され始めました。現在主流となり始めている変異株はEG.5.1との事、幸い上記ワクチンはこの変異株にも有効性が伝えられており9波が抑え込まれる効果を期待したいのですが、今後、医療抵抗力が強く増大した変異株の出現する可能性はあり得る事で専門家の間にも否定的見解は見当たりません。
このような状況を観ると新型コロナ感染症と私達との関係はpost coronaではなく未だ未だwith coronaにあると見通すべきです。通常、災害と言えば物的生活基盤、環境が損傷、破壊されるイメージですが今回の様な地球規模的感染症はそのようなことは全く無く、静かにヒトの体を襲い従来の生活様式の中では止めどなく伝染して行く天災です。即効的医療体制が準備されていない状況では対策として社会活動の制限、停止という手段を取らざるを得ずその副作用として社会活動の低下、混乱を招き時に分野的崩壊が生じると言う難しく辛い経験をしました。難しいのは社会活動制限の程度です。制限を強くすれば感染抑制の効果は上がる反面、副作用が増大し社会崩壊にも成り兼ねません。
この事に関連した私の勝手な想定で通常あり得ない事ですが、我々が専門医療として日常的に行っている難治性悪性腫瘍への抗がん剤治療を治験が全く無い状態で行うという行為が想像されます。抗がん剤治療は効果と安全性確認のため治験という段階を経る事は周知の事ですが、今回のパンデミック感染症に対する個々の対策は、出会ったことのない未知の癌に治験無しで手探りの実地癌医療の実施を余儀なくされている事に類似しているのではないかと思います。制限を強くして感染の消滅、除去を目指したと思われる中国でのゼロコロナ政策は副作用が大きくゼロ達成前の2022年に制限解除されましたが、現在も国内外への社会的悪影響は回復していないと言われています。一方with corona政策を続けた他国では社会活動、経済が段階的に回復している状況と思われます。中国での痛い経験は世界で貴重な経験として生かされるべきでしょう。
今後のwith corona 下の生活に於いて医療者に求められる事は第一線医療機関でコロナ感染の迅速な診断、コロナ陽性者への有効な治療薬の処方、必要な期間の外出自粛の指導、ワクチン接種を推奨し重症化と感染拡大を防ぐことに依って入院患者の増加を防止し医療崩壊を防ぐことでしょう。医学者、医薬品開発者には抗インフルエンザ剤創薬の過程で見られた様な多種の簡便な服薬法、より有効な薬剤の開発が期待されます。ワクチンに関しては、ウィルスの変異に依って効果に差が出ない有効なものが待ち望まれます。また、既存ワクチンの有効性が少ないヒト感染性の変異ウィルスが出現した場合に備えてより早く有効なワクチン開発が可能なシステムの構築が切望されます。
一覧に戻る
2023.11.14
同門会誌 令和5年度:巻頭言
教室代表挨拶
臨床家にしかできない基礎研究を
横浜市立大学医学部
血液・免疫・感染症内科学
主任教授 中島 秀明
1.教室の現況
本年度は血液2名、リウマチ1名の新入局者を迎えました。例年より少なめなのはパンデミックによる教室見学自粛などによる一時的な影響だと思いますが、その分選りすぐりの人材が入ってきたものと思います。診療面ではパンデミック下であったにもかかわらず、付属病院血液・リウマチ・感染症内科の新入院患者数、のべ入院患者数、入院・外来診療単価、入院・外来稼働額は順調に伸び、過去7年間の最高額を更新しました。また定床に対する病床稼働率もコンスタントに110-120%を維持しています。これらは全診療科の中でも1−2を争う数字であり、病院経営への貢献は計り知れないものがあります。これも一重に教室員全員の頑張りのおかげだと思っています。加えてCAR-T細胞療法やゲノム医療、血管再生療法といった先進医療でも病院を牽引しており、当院だけでなく名実ともに神奈川県全体の医療をリードしていると言えます。
一方で、働き方改革による勤務状況改善は待ったなしの状況で、勤怠管理も来年度から厳格化されます。当科では大幅な超過勤務は見られていなものの、限られた人員での診療はぎりぎりのバランスの上に成り立っており、たった1名の休職や離脱がこのバランスを崩してしまいかねません。このような現状を改善するのは我々自身の改革も重要ですが、教室単位での取り組みは自ずと限界があり、病院全体としてresilienceの高い組織に作り替えていくことが喫緊の課題です。
研究面はこのような困難な状況下でも着実に発展しています。基盤Bなどの大型科研費、AMEDの代表・分担を複数獲得しており、また企業や基礎教室との共同研究も多数進行しています。2018年に本格的に立ち上げた國本君を中心とする血液基礎研究グループも順調に発展し、学会シンポジウムで発表するまでになりました。大学院生3名も着々と成果を上げつつあります。リウマチグループは桐野君、吉見君を中心とした疾患研究が活発に行われ、特に自己炎症疾患研究は全国的な注目を集めています。感染症では寒川君の基礎研究や加藤君のCOVID関連の臨床研究が発展しました。今後は、臨床研究はもちろんのこと、これらの疾患基礎研究が日本の医学研究をリードしていってほしいと思います。
2.臨床医の視点から、臨床家にしかできない基礎研究を
この原稿を書いている最中に、mRNA医薬を開発したカタリン カリコらが今年のノーベル医学・生理学賞を受賞しました。カリコ博士は40年以上にわたりmRNAの医薬品応用を研究し続け、その成果がついに新型コロナウイルスワクチンとして花開き今回の受賞に至りました。彼女の辛苦に満ちた研究人生は本当に想像を絶しますが、幾度もの逆境を乗り越えmRNA医薬を実用化に導いた強い信念と行動力には心から敬意を表します。カリコ博士はPhDであるにも関わらず医学的な視点を常に忘れず研究を継続したことが、今回の栄誉につながったものと思います。
さて本題の医学研究ですが、医学研究と一口に言っても臨床研究、基礎研究、トランスレーショナルリサーチなど様々な種類があります。またその手法も、臨床研究では観察研究や介入試験があり、また基礎研究では生化学・分子生物学実験や動物実験などから生命現象・疾患のメカニズムに迫るいわゆるwetな研究、患者や疾患サンプルから得られたデータを活用したdryな研究まで千差万別です。この中で、我々臨床教室の人間が最も行うべきは、誤解を恐れずに言えば「臨床家にしかできない基礎研究」であると私は考えています。こう言うと「臨床研究は重要ではないのか」と言う声が各所から聞こえてきそうですが、もちろん臨床医として臨床研究は当然行うべきものの一つです。その上で私は、「臨床家にしかできない基礎研究」を一人でも多くの人に行ってほしいと願っています。
「臨床家にしかできない基礎研究」とは、簡単に言えば臨床家の視点から行う疾患基礎研究のことです。我々臨床家は、診療の最前線で日々多くの患者様に向き合い、病気を最も身近に感じています。様々な疾患について、今何がわかっていて何がわかっていないのか、どのような治療法・診断法が求められているのか、患者様や診療現場のunmet needsは何なのか、これらをもっともよく理解しているのは我々です。これはとりも直さず、我々がこのような疑問の解明・解決の糸口にもっとも近い場所にいるということです。また日々患者様を診療している我々は、貴重な研究サンプルを患者様からいただくことができます。これは基礎系研究者や企業がもっとも羨む、我々の大きなアドバンテージなのです。だからこそ、これらを活かして「臨床家にしかできない基礎研究」を行い、疾患メカニズムの解明から新しい治療法につなげることことは我々の責務ではないかと私は思うのです。こんなことを言うと多くの人は、それは基礎研究者の仕事で自分には関係ない、診療で多忙な自分たちにそんな大変な仕事をする時間はない、そもそも自分は基礎研究に興味はない、と言うかもしれません。でも考えてみて下さい。病気を何とかして治したい、課題を解決したいというモチベーションは、実は臨床家である我々がもっとも強いのではないでしょうか。そのような我々にとって、研究を通じて患者さんの役に立つような成果をあげることは、目の前の患者さんの病気を治すのと同じぐらいやり甲斐のあることだと思います。
堅苦しいことを言いましたが、もとより研究はとても楽しく、思わずのめり込んでしまうような知的作業です。もちろん苦労や挫折も沢山ありますが、大きな発見をした時の達成感は何ものにも代えがたく、それまでの苦労が全て吹っ飛んでしまうほどの喜びがあります。そして頑張った結果が患者さんの役に立つとなれば、これは研究医師、すなわちphysician scientist冥利につきると言えるでしょう。
私がいつも口にしている「研究は目に見えない患者様のために」はまさにこのようなことを指しています。目の前の患者さんの診療に追われていると、限られた数の患者様しか救えません。一人でも多くの人が「臨床家にしかできない基礎研究」の世界に飛び込み、未来を変えていってくれることを願っています。
一覧に戻る
2023.11.14
同門会誌 令和5年度:巻頭言
医局の近況について
血液・免疫・感染症内科学
医局長 吉見 竜介
いつも大変お世話になっております.2020年1月より当教室の医局長を担当させていただいております.私が医局長を担当し始めたとほぼ同時にCOVID-19が流行し始め,以来長い間,当医局もその影響を様々な形で受け続けてまいりました.本年5月8日,ついにCOVID-19は5類感染症に移行し,社会はようやく少しずつですが日常を取り戻してきています.当医局においても,7月6日に同門会総会および納涼会を,実に4年ぶりにオンサイトで開催することができました.多くの同門の先生方と久しぶりに直にお会いしてお話を伺える機会をいただき,とても楽しい時間を過ごさせていただくことができました.
学部生の教育においてもオンライン中心から対面形式中心に移行し,病棟実習もほぼコロナ前と同じように行えるようになっており,学生の学びの場,教員と学生の交流の場が戻ってきました.研究においては,コロナ前後も変わりなく多くの大学院生が研究活動を頑張っており,実験室内は活気を保っています.また,関連病院の先生方が研修医向けのリクルート活動にご尽力下さったことが実を結び,来年度は当科全体で6名(血液グループ2名,膠原病グループ4名)の先生に御入局いただくことになりました.診療の現場では,通院患者さんのCOVID-19発症が散発し,9月には当科の病棟でクラスターが発生するなど,まだまだ気を引き締めていくべき状況ではあります.しかし,長いトンネルの暗闇の先にある外の光が,ようやく私達にも見えてきたのではないかと思います.
COVID-19の流行は人々の生活様式を大きく変化させました.未曽有の大災害ではありましたが,未来に向けてこの経験をプラスとなるようにしていくことが重要であると考えております.社会では様々な部分で効率化が進んでいます.会議や研究会,学会のオンライン化やハイブリッド化は,参加する機会を増やし,移動の労力を削減しました.COVID-19とは直接関係はありませんが,来年度には医師の働き方改革の新制度が施行されます.私達も自分たちの業務の効率化というものをより一層意識的に進めていく必要があろうかと思います.当医局のさらなる発展・進化に向けて,努力してまいります.今後ともご指導の程何卒よろしくお願い申し上げます.
一覧に戻る
2023.11.14
同門会誌 令和5年度:巻頭言
特別寄稿:横浜市立大学医学部 膠原病グループ開設五十年を振り返って
横浜市立大学名誉教授 石ヶ坪 良明
表題のテーマで原稿を依頼されたが、まず、私が入局した当時の第一内科のグループについて紹介する。当時、研修終了後、第一内科に入局すると、2年間は、総合内科医としての経験を積むべく、①呼吸器、②消化器、③循環器、④その他(膠原病、血液、内分泌・神経など)の4つのグループに半年ずつ所属し、研修することが義務付けられていた。そこでは、各Gに特化した胸部、胃xpなど画像読影、気管・胃などの内視鏡およびECG判読などが日課として要求されていた。
上述のように、現在の膠原病や血液は、当時の第一内科では、その他のグループに属していた。
膠原病Gは、昭和46年卒の谷賢治先生が昭和48年の入局後に、最初に患者さんの診療を始めた。谷先生とは、東洋医学研究会のサークルの先輩・後輩の関係で、私が昭和50年の研修1年目から、週1回の専門外来診療に勧誘され2人で患者さんを診療することになった。当時は、数名のSLE患者さんを二人で診療し、週によっては、0人の日もあったが、2年後には30名程度のSLE患者さんが受診するようになった。谷先生の温厚かつ包括力豊かな人柄もあり、その約2年後には、千場、加藤、松永先生、その後、さらに、長岡、成田先生なども参加し、次第に大きなグループになり、私が定年時には50名を超えるグループに成長した。
膠原病グループの特徴としては、当時からJEM、JI、Nature、Scienceなどに掲載されている免疫関連分野の抄読会を通じて新しい免疫学の知識を共有する研究志向の仲間が主体であった。
その伝統を継承して、研究面での興味を維持しながら、臨床に取り組んでいると聞いている。そのような経緯を踏まえ、膠原病Gの留学者は20名を超える。
現在、大学在籍者のなかでも、NIHのCheucetのラボに大野先生、Kastnerのラボに桐野、仲野先生、小畑先生のラボに吉見先生が留学して膠原病の伝統を引き継いでいただいている。
その中で、膠原病Gのみならず、当時の旧第一内科(膠原病、血液、感染症、呼吸器)の同僚の皆さんが、大学および地域の中核病院で活躍されていることも取り挙げたい。
膠原病グループでは、病院教授(青木、岳野、大野)、看護大学教授(白井)を含め5人の教授および南共済(長岡)、大和市立・三浦市民(五十嵐)、聖ヨゼフ(白井)、横須賀市民などの病院長、血液Gからも、冨田教授および丸田先生を起点に神奈川県立がんセンターにて4代連続での病院長(丸田、本村、金森、酒井)、呼吸器Gからも金子教授、小田切、長谷川先生を起点に、循環器呼吸器病センター(小田切)、藤沢市民病院(長谷川、西川)、南共済病院(高橋)などの中核拠点病院の院長職に就任されている。また、感染症グループは、福嶋教授時代から神奈川感染症医学会、さらに、HIV診療を通じて神奈川、横浜の感染症領域を牽引してきた。
紙面の都合で詳細が述べられないのは残念だが、今後も、膠原病、血液、感染症グループはもちろん、旧第一内科の皆さんが、互恵の念で切磋琢磨して発展していただけることを願っている。
一覧に戻る
2023.11.14
同門会誌 令和5年度:巻頭言
附属病院・血液グループ 近況報告
横浜市立大学医学部 血液・免疫・感染症内科
講師 松本 憲二
同門会の皆様には診療および医学研究につきまして、日頃よりご指導とご支援を賜り、誠にありがとうございます。附属病院・血液グループの近況をご報告申し上げます。
附属病院では中島教授を中心として、血液診療スタッフ医師と大学院生が在籍しており、血液臨床と基礎研究を行っています。血液診療においては本年度もCOVID-19の影響は続いており、一旦収束の兆しが見えていたものの、COVID-19感染が血液疾患患者に与える影響は小さくなく、ウィズコロナ時代では血液診療でも特に免疫が長期間に抑制される移植治療や細胞療法において、今後長期間にわたり影響が続き困難をきたす症例も一定数あるであろうと実感しています。2年前から始まったCAR-T細胞療法については順調に症例数を増やしていると共に、神奈川県内で運用している施設が少ないという現状から、さらに二製剤の採用に向けて準備が進めています。準備が整った際には地域のリンパ腫診療に大きく貢献できると考えています。研究面では患者様の細胞を用いたクリニカルシークエンスの解析が稼動して症例数が蓄積しており、臨床判断にも反映されるようになってきました。さらに骨髄異形成症候群についての患者データベースの整備によって充実した研究体制の構築を目指しております。数年前に開設された患者サポートセンターが年々充実してきて、地域医療への強化・推進が図られていますが、日常診療においても横浜南部地域や横須賀方面の高齢化を反映して、診断されても合併症や年齢によって治療を完遂できない症例も増えており、ますます地域医療との連携の重要性が増していると痛感しております。臨床研究においても研究倫理や医療情報管理の面で課題も多く残っており、日々の精進をより一層心がけていく必要があると考えられます。
同門会の皆様におかれましては益々のご協力とご指導をお願いすることになると思いますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
一覧に戻る
2023.11.14
同門会誌 令和5年度:大学の現況
附属病院・膠原病グループ 近況報告
横浜市立大学医学部 血液・免疫・感染症内科学
講師 桐野 洋平
同門会の皆様に置かれましては、附属病院のリウマチ膠原病診療および研究の支援を賜り誠にありがとうございます。膠原病グループの近況をご報告致します。
膠原病グループのスタッフ数は42名となりました。本年度は橋本詠仁(横浜市立大学出身、横浜医療センター勤務)の1名が新たに加わりました。すでに来年度の入局者も4名内定しております。各関連施設におけるポジションも増えつつあり、ますます臨床・研究の質の向上が期待されます。
入局者が増加している理由は複数あると思いますが、近年のリウマチ膠原病治療の進歩による劇的な予後改善は大きく寄与していると考えます。関節リウマチの治療戦略は、寛解はもちろん、drug-free寛解を目指す方向へ変化しつつあります。関節リウマチで寝たきりになる方は、新規発症例ではまずいません。全身性エリテマトーデス、血管炎などでも新規薬剤が次々に登場しています。入院したときは重症だった患者さんが、よくなって社会復帰していく姿を目の当たりにし、リウマチ診療に魅力を感じる研修医が多いのではないでしょうか。入局者が増えている理由として、若手スタッフの活力も挙げられます。附属病院には現在17名の膠原病グループのスタッフが在籍し、うち大学院生は8名です。彼らは研究以外にも、学会、臨床、教育に自発的かつ積極的に参加しており、当グループの大きな原動力となっています。彼らのはつらつとした姿に共感する研修医もいるのではないかと思います。留学も積極的に推進しており、2018年より約5年間留学していた仲野が帰国し、代わりに2023年6月より國下が米国NIH/NIAMS Kastnerラボに留学しております。最後に、先輩方から脈々と50年間にわたり引き継がれてきている横浜市大膠原病グループの安定感、団結力、伝統、そして医局全体の活力も魅力になっていると感じます。本年10月7日、膠原病グループ結成50周年記念会も開催されました。こちらの詳細については別途報告があると思います。
研究面ですが、2023年度は10月19日現在当グループが主体となって作成した論文3本が掲載/受理されています。本年度はハイインパクトな論文が複数掲載されております。前田大学院生らによる本邦のVEXAS症候群のUBA1遺伝子解析報告 (Rheumatology)、免役チェックポイント阻害剤の関節症状に関する調査(Rheumatology)、秀川大学院生らによる全身性エリテマトーデスにおけるヒドロキシクロロキンの感染症予防効果(Frontiers Immunology)。その他2本の論文が投稿中または投稿準備中です。印象的なのは専攻医や大学院1-2年目のスタッフが論文を次々と公表していることです。コロナ蔓延にてなかなか直接ご報告する機会がありませんが、このような充実した研究活動を継続して行きたいと考えておりますので、引き続きご指導の程よろしくお願い申し上げます。

2023年度 附属病院 膠原病グループスタッフ
一覧に戻る